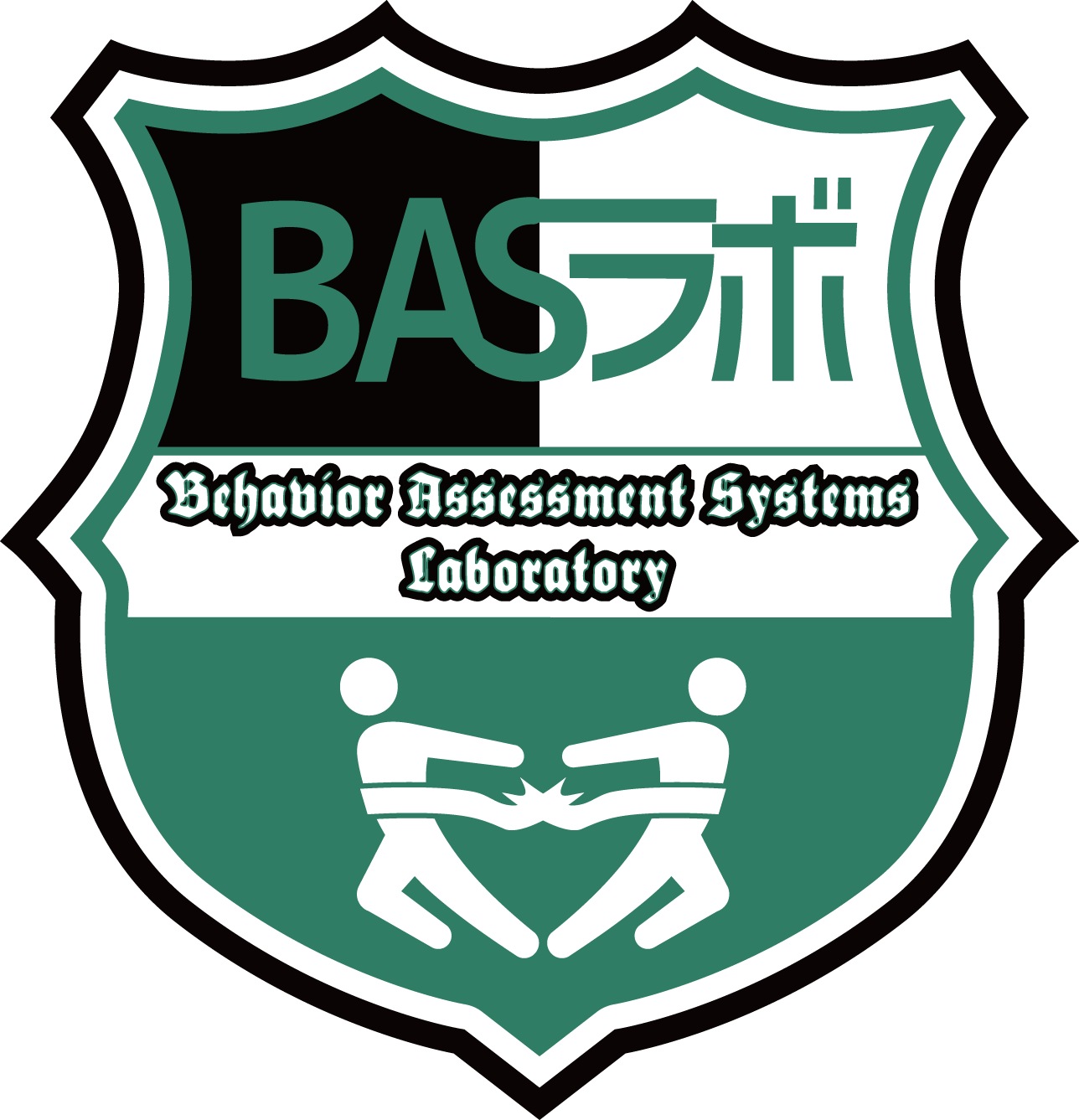メンバー紹介
河津慶太博士 研究員

一般社団法人行動評価システム研究所(BASラボ)メンタルトレーニング部門プロフェッショナルトレーナーの河津慶太です。
スポーツ心理学、特に集団スポーツにおけるチームワーク研究を専門としています。
日本スポーツ心理学会認定スポーツメンタルトレーニング指導士(以下、SMT指導士)としてエビデンスに基づいたメンタルトレーニングを提供しています。
関連)日本スポーツ心理学会 スポーツメンタルトレーニング指導士
集団スポーツとチームビルディング
スポーツ心理学は、スポーツに関わる課題を心理学的側面から明らかにして、
スポーツの実践や指導に科学的知識を提供する学問です。(詳しくは磯貝浩久教授を参照)

私の専門であるチームワーク研究では、
バレーボール、バスケットボール、サッカー、ハンドボールなど…集団スポーツのチームが対象となります。
これらのスポーツでは、状況が秒単位で変化する試合のなか、アスリートは敵味方双方の状況を把握しつつ未来を予測し、決断と行動を繰り返しています。この時に求められるスキルをオープンスキルと言います。
※スポーツにおける2つのスキル
「オープンスキル」…刻々と変化する状況の中で役立てるスキルのこと。状況判断/予測力/決断力など
「クローズドスキル」…フリースロー、サーブ、PK 固定された状況で発揮される技術や能力のこと。
オープンスキルが重要になってくる集団スポーツにおいて、チームワークはチーム全体のパフォーマンスを大きく左右することがわかっています。
このチームワークを作り上げ、一つの目標に向かっていくためにチームに介入する方法を「チームビルディング」と言います。
以下で事例を交えてご紹介します。
2024車いすラグビー日本代表

出典:パラサポWEB
パラスポーツとして有名になった車いすラグビーですが、実際にご経験された方は少ないと思います。
私も少し体験させていただきましたが、選手同士がぶつかる衝撃は想像以上に激しく、凄まじいスポーツで驚きました。
2024年パラリンピック日本代表チームには、SMT指導士としてチームビルディングを実施しました。
このチームはご周知のとおりパリで金メダルを獲得し、私も現地に帯同しとても感動しました。
もっとも、メンタルのサポートは現地に到着するまでが仕事のほとんどと言え、現地では大したことはしていませんが…。
車いすラグビーは障害等級がポイント化されておりそれぞれ0.5〜3.5点の持ち点が与えられています。
障害が重ければローポイント、障害が軽ければハイポイント。
4人の合計ポイントが8ポイントを超えてはならないルールのもと、男女混合・障害等級も多彩な選手でチーム構成されます。
さらに40代後半の選手も珍しくなく、選手間の年齢差も大きくなります。
このような車いすラグビーのチームでは、チームワークを高めていくことも大変です。

そこでチームワークを高めるためのチームビルディングが求められました。
日本代表チームには大会の1年半ほど前から関わり、時間をかけてチームビルディングを行いました。
まずは選手が互いを知るための自己開示(自身の内面を率直に開示)の時間から始めました。
国内のトップ選手として選ばれた人たちで構成される代表チームでは、競技の話をすることは多くあるのですが、それ以外の自分についての話(趣味、プライベートの話)はあまり話さないものです。自己開示をするためには、競技とは関係のない話の方が効果的です。
その後は、競技に関するようなテーマも設定しながらミーティングやグループワークを積み重ねていきました。
さらに、話し合ったことを実際の行動へと落とし込んでいき、パリ大会に向かってチームワークを育てていきました。
この過程で「自分たちならできる」という強い集団効力感₁ ₂も醸成されていきます。
ひとつひとつ大切に積み上げていく、言葉どおり「チームビルディング」なのです。
- 1)集団効力感collective efficacy/カナダ人心理学者アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)が提唱した概念。バンデューラは史上最も影響力のある心理学者の一人と評価されている。
- 2)関連研究 河津 慶太, 杉山 佳生, 中須賀 巧 スポーツチームにおける集団効力感とチームパフォーマンスの関係の種目間検討 2012 年 39 巻 2 号 p. 153-167
メンタルサポートの理想とは

パラバドミントン,プロバスケライジングゼファー福岡、フットサル ボルクバレット北九州のメンタルサポートも担当しました。
メンタルサポートの理想は、サポートされる側の人が「もうサポートは要りませんよ」と自立することです。
これは妙な言い方に聞こえるかもしれませんが、自立とは自分で必要なものを知っていること。
なんでも自分ひとりで背負い込むこととは違います。
自分のチカラではどうしようもないことを認識でき、他者に頼める状態のことを指しています。
近年メンタルの重要性もかなり認知はされてきていますが、活用されているかというと…まだまだな現実もあります。
残念ながら日本スポーツ心理学会認定のSMT指導士はまだまだ知られていません。
一方で、スポーツメンタルについては様々な情報が飛び交っている部分があります。
私たちBASラボは学術エビデンスに基づいたメンタルサポートを広く一般に提供していきたいと考えています。
BASラボの理念「研究からフィールドへ」を広く実践していきたいですね。
メンタルとフィジカルのバランス

メンタルの重要性についてお伝えしていますが、フィジカルを優先して考えるべきケースも多く存在します。
様々な選手からの相談に対応していますと、
「まずはしっかり寝て休んだ方が良いのでは」と、まずは疲弊してしまっている身体をケアした方がうまくいくだろうな、という状態の選手も多いのです。
メンタルを整えるためには、まず身体のリラックスを優先すべきです。
これは、練習や試合後のケアの時だけでなく、試合中の感情コントロールにおいても同様のことが言えます。
ちょっと変な例えですが、ドラえもんがパニックを起こして四次元ポケットからあらゆる道具を出しまくって混乱しているときがありますよね。
そういう時は、「ドラえもんおちついて!ゆっくり考えよう!」というような、感情のコントロールを意図した声掛けよりも先に「ドラえもん、まずはその手を止めようか。それからゆっくり深呼吸してみて」と言ってあげたほうが落ち着きやすいものです。
直接的なメンタルに対するアプローチだけで全てを解決できるわけではありません。このあたりが学術エビデンスに基づいた
バランスをもって捉えていきたい部分だと思っています。
一般の人に知ってもらいたい
一般の人に広く知ってもらいたいと思い執筆した本が【生き方が楽になるハイキューの言葉】です。
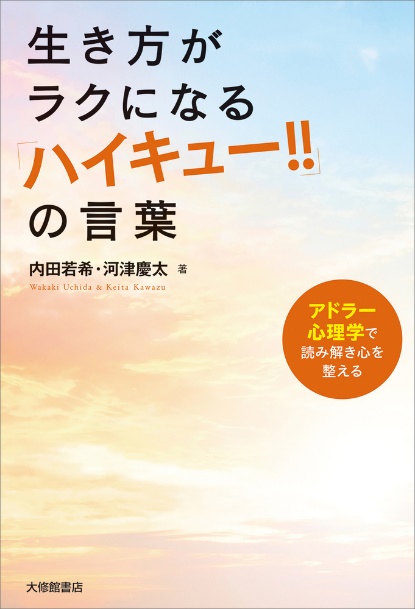
内田若希/河津慶太 著 出版年月日2024/01/17 ISBN 9784469269741
購入はこちらから amazon
この本はスポーツマンガを題材にしていますが、スポーツだけではなく一般の多くの皆さんに伝えたいお話をまとめています。
生きていくことが、とても息苦しくおもったり、困難を感じてしまったりする方に、アドラー心理学やスポーツ心理学などの知見を元に生き方がラクになるお話をしています。
メンタルトレーニングは一般の方々にとって「予防的な」お話です。
心の問題が発生した人の解決に取り組む臨床心理士や、治療にあたる心療内科医と最も異なるのはこのあたりですね。
小学校中学校の保護者を対象に子育て支援講演することもあります。
スポーツ心理学で得た知見を広く一般の方々に。
BASラボの「研究からフィールドへ」を実践してまいります。ご期待ください。

河津 慶太 PROFILE
九州大学大学院にてチームワーク研究により人間環境学博士号を取得。日本代表/プロチームからローカルな選手まで各年代選手の心理サポートを担当。そのかたわら、ストリートパフォーマーとしても有名。九州大学学術協力研究員/JPC医科学情報サポート心理スタッフ/日本スポーツ心理学会スポーツメンタルトレーニング指導士/一般社団法人行動評価システム研究所プロフェッショナルトレーナー。